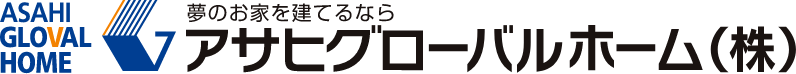| 【四日市】 | Tel.0120-541-008 |
|---|---|
| 【桑名】 | Tel.0120-932-144 |
| 【鈴鹿】 | Tel.0120-002-047 |
| 【津】 | Tel.0120-080-311 |
| 【一宮】 | Tel.0120-597-011 |
| 【尾張旭】 | Tel.0120-02-8670 |
| 【春日井】 | Tel.0120-96-9466 |
| 【岐阜】 | Tel.0120-920-769 |
営業時間 10:00〜18:00 定休日 火曜日
- ホーム
- 耐震性

耐震性
ご家族の命と暮らしを守り続けたい。「耐震」+「制震」で安心安全な住まいづくり
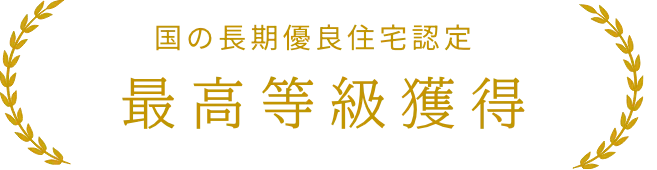

耐震等級3とは
非常にまれな頻度(数百年に一度程度)で発生する地震に対して、 通常の地震の1.5倍の力にも耐えることができるレベルを指します。これは、建物が倒壊しない程度を意味します。
※長期優良住宅仕様に限ります。詳しくはスタッフまでお問い合せください


最大95%の揺れを低減 ミライエ住宅用制震ユニット「MIRAIE」
強い揺れ・繰り返しの揺れに最大限の効果を発揮。本震はもちろん、繰り返す余震にも強いお家に。