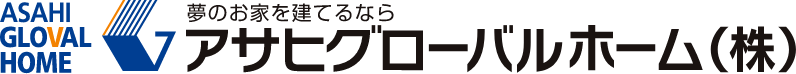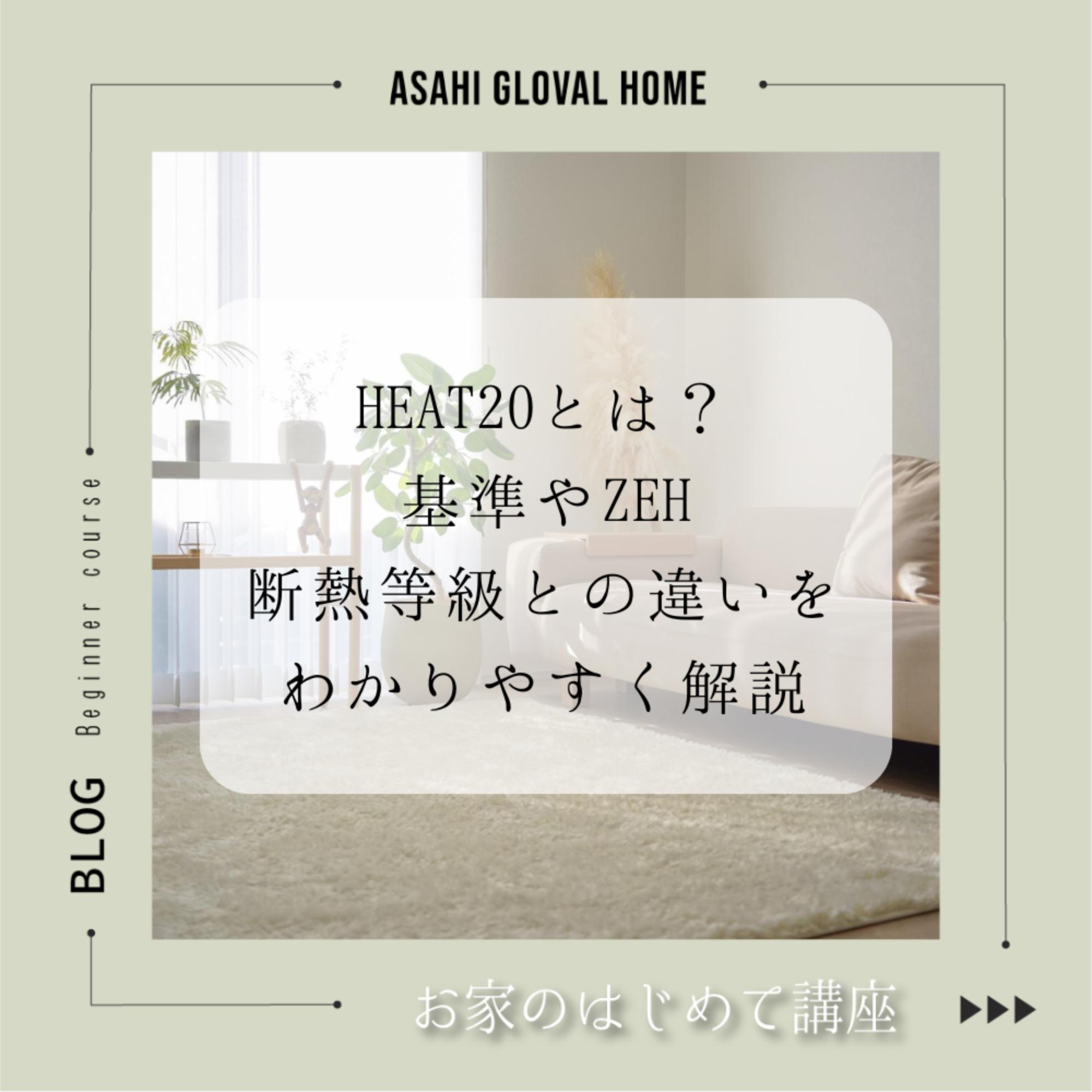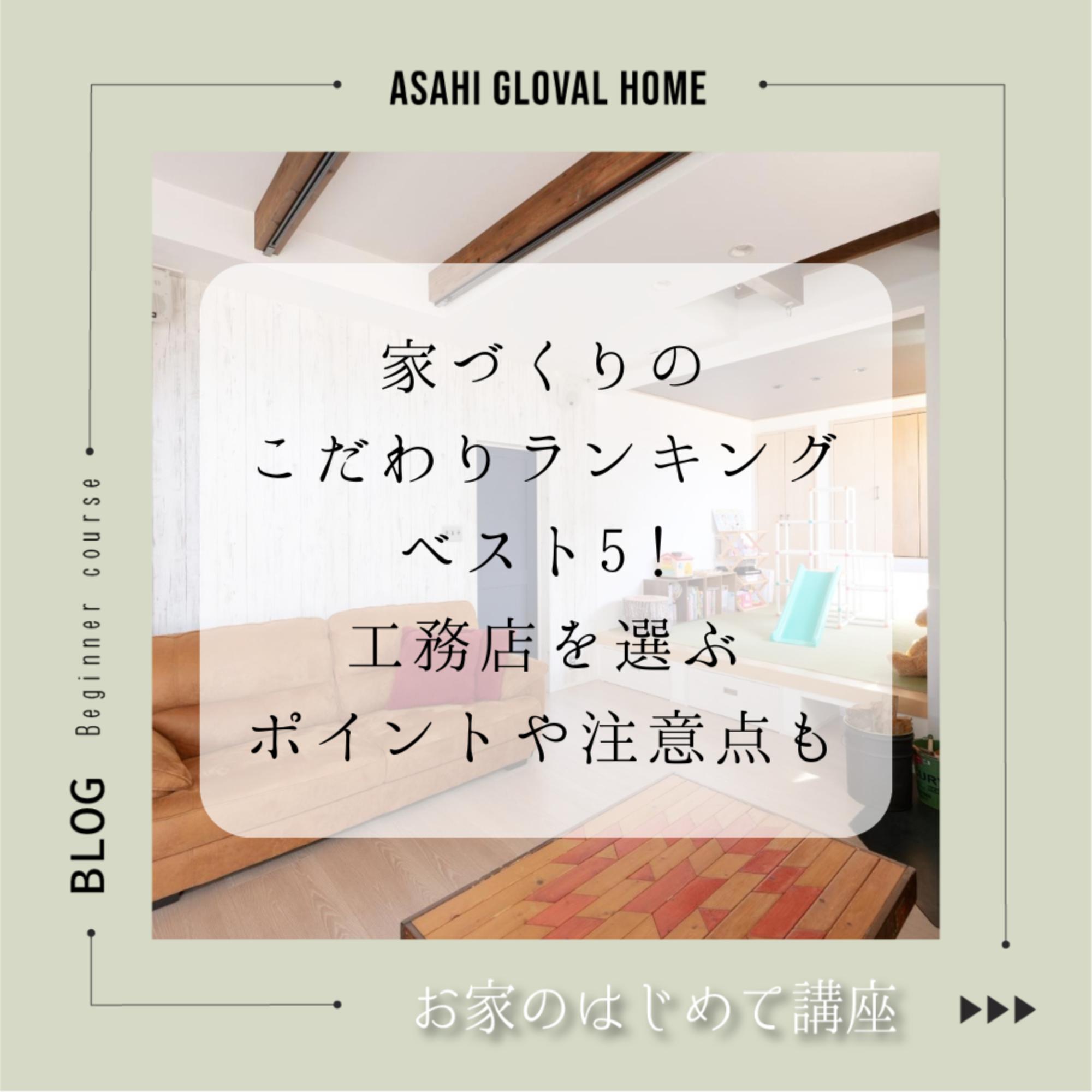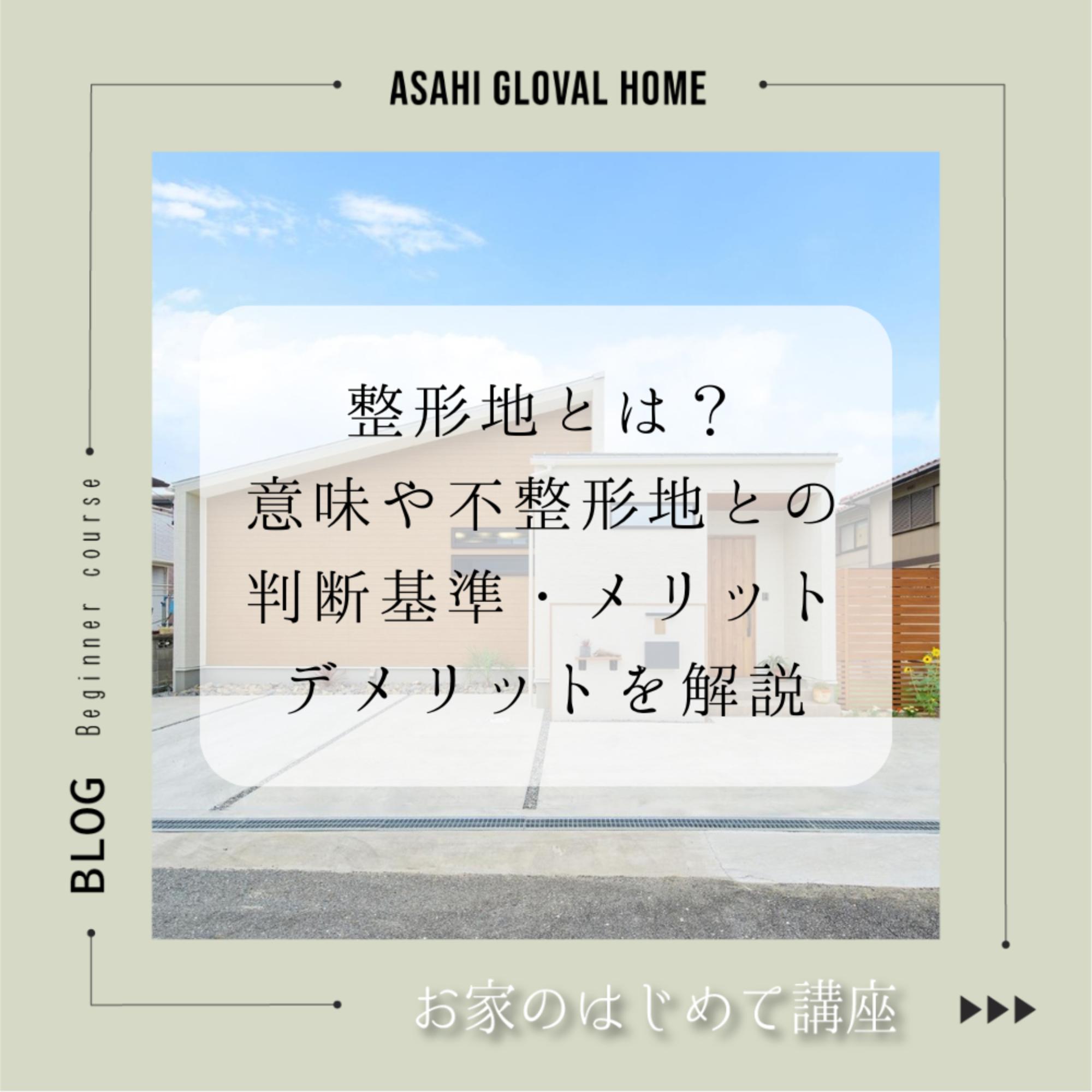公開:2025.04.28 更新:2025.05.15
住宅の湿気対策はどうする?壁や床におすすめな建材や家づくりのポイントも

家づくりを進めるなかで、「住宅の湿気対策はどうする?」と疑問を感じる方も多いでしょう。
住宅に湿気が発生する原因には、屋外から侵入する雨水や地面から上昇する水分、結露などが考えられます。
湿気がこもりやすい環境の場合、壁や床などの建材にカビが発生して、住宅の耐久性や性能を低下させるおそれがあるので注意が必要です。
そこでこの記事では、壁や床の湿気対策について解説します。
結露が起きる原因と壁や床に調湿建材を使用するメリット・デメリットも紹介するので、家づくりの参考にしてください。

【来場特典の対象者は以下のすべての条件を満たすお客様のみとさせていただきます】
・担当からの予約確認のお電話に、ご来場希望の2日前までの9時-18時の間にて対応いただくこと
・事前・来場後各種アンケートの質問に全てお答えいただくこと
・来場希望日の【3日前】までに、ご予約の上ご来場いただくこと
・初めて当社へのご来場であること
・ご来場時に本人確認書類(運転免許・健康保険など)を提示いただけること
・入居予定の成人の方が全員ご来場いただくこと
・外国籍の場合は永住権があること
・当日のご案内・ご提案時間を60分以上確保して場いただけること
・弊社対応エリア内で1年以内にお家づくりをご検討の方
※ご来場イベントのエントリールールに則ってご来場いただけなかった場合や、ご相談の内容により建築のご予定がないと当社にて判断させていただいた場合にご来場特典の送付を中止させていただく場合がございます。
※特典は「メールでのお届け」となります。(ご来場日から1ヶ月程お時間を頂いております)
目次
結露が起きる原因は屋内と屋外の温度差

湿気の原因の1つである「結露」は、屋内と屋外の温度差によって発生します。
具体的には、湿気を含んだ暖かい空気が冷やされた壁などに触れることで、余分な水蒸気が水滴に変わる仕組みです。
たとえば、屋内外の暖かい空気が壁の内部に侵入し、外気や冷房によって冷やされた壁に触れて結露が発生します。
結露は冬だけでなく夏にも起こる可能性があるので、対策が必須です。
内部結露によって柱や土台が腐るおそれがあり、住宅の耐久性が低下する原因となります。
湿気対策には高気密高断熱な施工が不可欠
住宅の湿気対策には極端な温度差を防ぎ、湿気を含んだ空気が侵入しないようにする必要があり、高気密高断熱な施工が欠かせません。
また、室内の湿気を排出する換気計画も重要です。
住宅の湿気をコントロールするためにも、調湿機能の高い建材の利用を検討しましょう。
壁や床におすすめしたい調湿建材は次の章で紹介します。
住宅における気密性の本当の重要性についてもっと知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
【関連記事】住宅における気密性の本当の重要性とは?快適な家づくりのポイントを解説
壁や床におすすめしたい調湿建材

壁や床の調湿性能を高めるには、以下の建材を利用するのが一般的です。
- 塗り壁
- 調湿効果のある壁材
- 無垢床のフローリング
- い草の畳
塗り壁の材料となる珪藻土や漆喰は多孔質であり、無数の小さな穴が湿気を吸収・放出することで、調湿効果を得られます。
以下のような調湿効果のある壁材を使用することでも、湿気対策が可能です。
- エコカラット
- さらりあ~と
- クールジャパン
調湿効果のある壁材は調湿性に加えて、抗菌・抗ウイルス性などの性能をプラスした多機能な種類もあり、さまざまな効果を期待できます。
そのほかにも無垢床のフローリングを採用したり、い草の畳を用いたりするのも調湿性の点では効果的です。
無垢床のフローリングは木材表面の小さな穴から湿気を吸収・放出しており、室内を快適な環境へ整えます。
無垢床とは、丸太から切り出した1枚の板を並べて作った床材です。
い草の畳は、繊維間の空気層が湿気を吸収・放出することによって、調湿効果を見込めます。
壁や床に調湿建材を使用するメリット・デメリット

ここでは、壁や床に調湿建材を使用するメリット・デメリットを解説します。
メリットだけではなくデメリットも把握して、「イメージと違った」などのミスマッチを回避しましょう。
壁や床に調湿建材を使用するメリット
壁や床に調湿建材を使用するメリットは以下のとおりです。
- 年間を通して室内の湿度を一定に保ちやすくなる
- 結露が起こりづらくなる
- 消臭・抗菌・抗ウイルスなどの効果も期待できる
- 自然の温もりを感じられる
調湿建材は湿気が多いときに吸収し、乾燥しているときに湿気を放出するため、年間を通して室内の湿度を一定にキープしやすくなります。
湿気をコントロールすることで、結露が発生しづらくなるのも嬉しいポイントです。
建材によっても異なりますが、消臭・抗菌・抗ウイルスなどのさまざまな効果を期待できる種類もあり、快適な住まいを目指せます。
珪藻土や漆喰を利用する塗り壁や、無垢床のフローリングなどを使用する場合は、日々の生活のなかで自然の温もりを感じられるのも魅力です。
壁や床に調湿建材を使用するデメリット
壁や床に調湿建材を使用するデメリットは以下が挙げられます。
- 費用が高くなるケースがある
- メンテナンスに手間がかかる可能性がある
- 張り替えが難しい傾向にある
高性能な建材や施工に手間がかかる建材は、費用が高くなりやすいので注意しましょう。
たとえば、漆喰を採用する場合には下地を塗るなど工程が多く、高額になる可能性があります。
自然素材を利用する際はメンテナンスに手間がかかるケースがあるため、考慮して取り入れることが大切です。
無垢床のフローリングを使用する場合は、仕上げ方法によっても異なりますが、オイルの塗布など定期的なメンテナンスが必要になります。
調湿建材は一般的なクロスのように気軽に張り替えができない傾向にあるため、「定期的に模様替えしたい」と考えている方はよく検討しましょう。
湿気対策がしやすい家づくりのポイント

湿気対策がしやすい家づくりのポイントをまとめました。
- 自然素材を使用する
- 外壁や屋根裏に湿気を逃がす空気の通り道を作る
- 基礎の断熱工法にこだわる
- 施工品質の高い工務店に依頼する
壁や床材を含めて、家づくり全体での湿気対策について解説します。
自然素材を使用する
湿気の多い場合に吸収し、乾燥している場合に湿気を放出する「自然素材」を使用して、快適な住宅を実現しましょう。
調湿効果を期待できる自然素材として、以下が挙げられます。
- 珪藻土
- 漆喰
- シラス壁
- 無垢床
- 板張り
- い草
- コルク材
上記のような自然素材を用いることで、最適な湿度をキープしやすくなります。
また、自然素材を取り入れるとナチュラルな雰囲気に仕上げられたり、時間の経過による風合いの変化を楽しめたりするのも魅力です。
外壁や屋根裏に湿気を逃がす空気の通り道を作る
外壁や屋根裏に湿気を逃がす空気の通り道を作ると、結露やカビの発生を予防して、建物の長寿命化につながります。
外壁では、暖かい空気を下から上へと自然に流す「外壁換気工法」を採用するのがおすすめです。
また、昼と夜の温度差が激しい小屋裏は棟換気口を設けて、熱や湿気を排出する方法があります。
基礎の断熱工法にこだわる
床下の温度と湿度をほぼ一定に維持して結露を防ぐには、基礎の断熱工法にこだわることも大切です。
基礎の断熱工法には基礎断熱と床断熱の大きく2つがあり、断熱材をどのように設置するかに違いがあります。
施工エリアによってどちらの断熱工法を選ぶべきかは判断が分かれますが、温度・湿度の保ちやすさという点で基礎断熱のほうがおすすめです。
基礎断熱と床断熱の違いについて理解を深めたい方は、以下の記事をご覧ください。
【関連記事】基礎断熱と床断熱の違いは?メリット・デメリットや後悔しない選び方を解説
施工品質の高い工務店に依頼する
湿気や結露の発生を防止する「高気密高断熱な住宅」を実現するためにも、施工品質の高い工務店に依頼しましょう。
工務店のホームページをチェックする際には、デザイン性はもちろん、技術力や施工品質も確認してください。
また、工務店との打ち合わせでは、結露のリスクや対策を聞いておくと安心です。
アサヒグローバルホームの湿気対策
アサヒグローバルホームの湿気対策を、当社が手がけた住宅の施工事例をもとに紹介します。
「どのような湿気対策を実施したらよいか分からない」とお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
当社が手がけた住宅の施工事例
こちらは、壁材に調湿性のある「エコカラット」を利用している事例です。
エコカラットは湿度の調節をはじめとして気になるニオイを吸収したり、有害物質を吸着したりする効果も期待でき、居心地のよい空間を目指せます。
また、こちらの住宅で採用しているエコカラットは高級感のあるデザインで、内装の雰囲気にマッチしているのもポイントです。

リビングにはサイズの大きな掃き出し窓を設けており、日当たりを確保しやすく湿気がこもりにくいデザインとなっています。
家づくりで後悔を回避するには、実際の住宅を見学して理想のイメージを掴むことも重要です。
当社の住宅を見学したい方は、展示場ページをご覧ください。
まとめ:調湿機能のある壁材で湿気対策を

調湿機能のある壁材や床材を利用すると、湿気や結露を防止して快適な住宅を実現できます。
たとえば、珪藻土や漆喰などの自然素材を採用すると、調湿効果を得ることが可能です。
加えて、湿気対策には高気密高断熱な施工が欠かせないので、実績が豊富な工務店を選びましょう。
アサヒグローバルホームでは、基礎断熱や断熱効果の高いアルミ樹脂複合サッシを取り入れるなど、調湿性にこだわって家づくりを進めています。
当社の家づくりについてもっと知りたい方は、資料請求ページより資料をお求めください。
【関連記事】建ててから後悔したくない!今知るべき無垢の家のメリット・デメリットとは?
【関連記事】工務店の選び方とは?理想の住まいを叶えてくれる会社を見極める5つの視点
【関連記事】断熱材とは?3つの種類と特徴・性能を徹底比較 | 選ぶ基準も解説